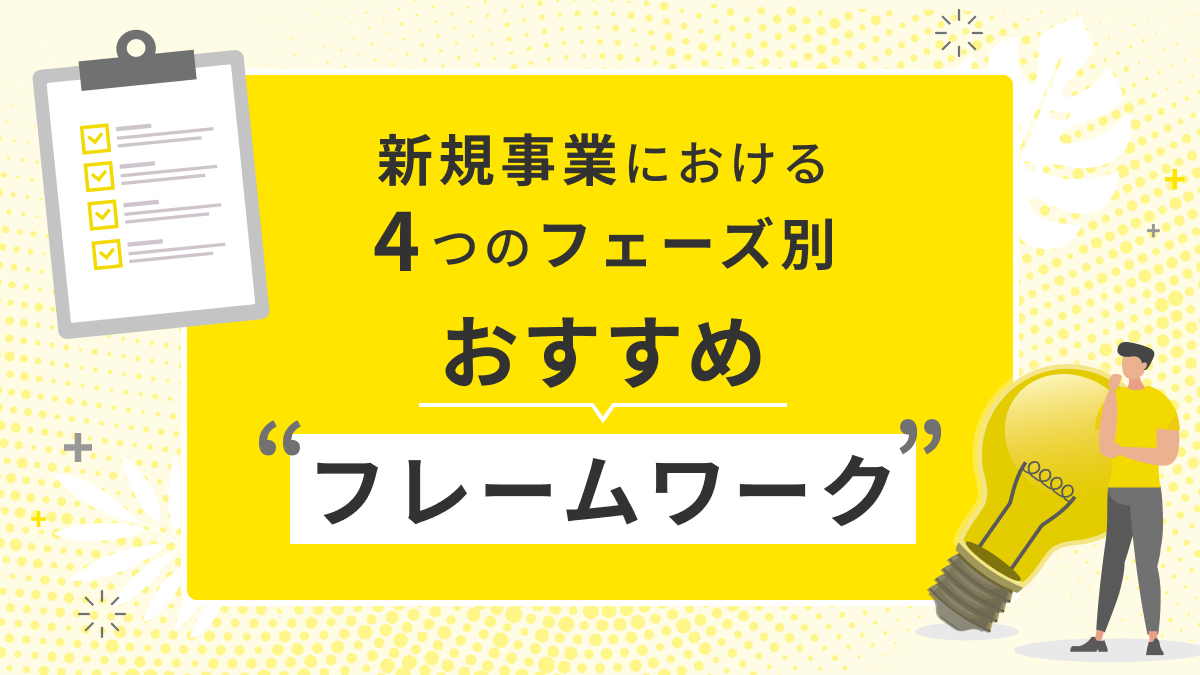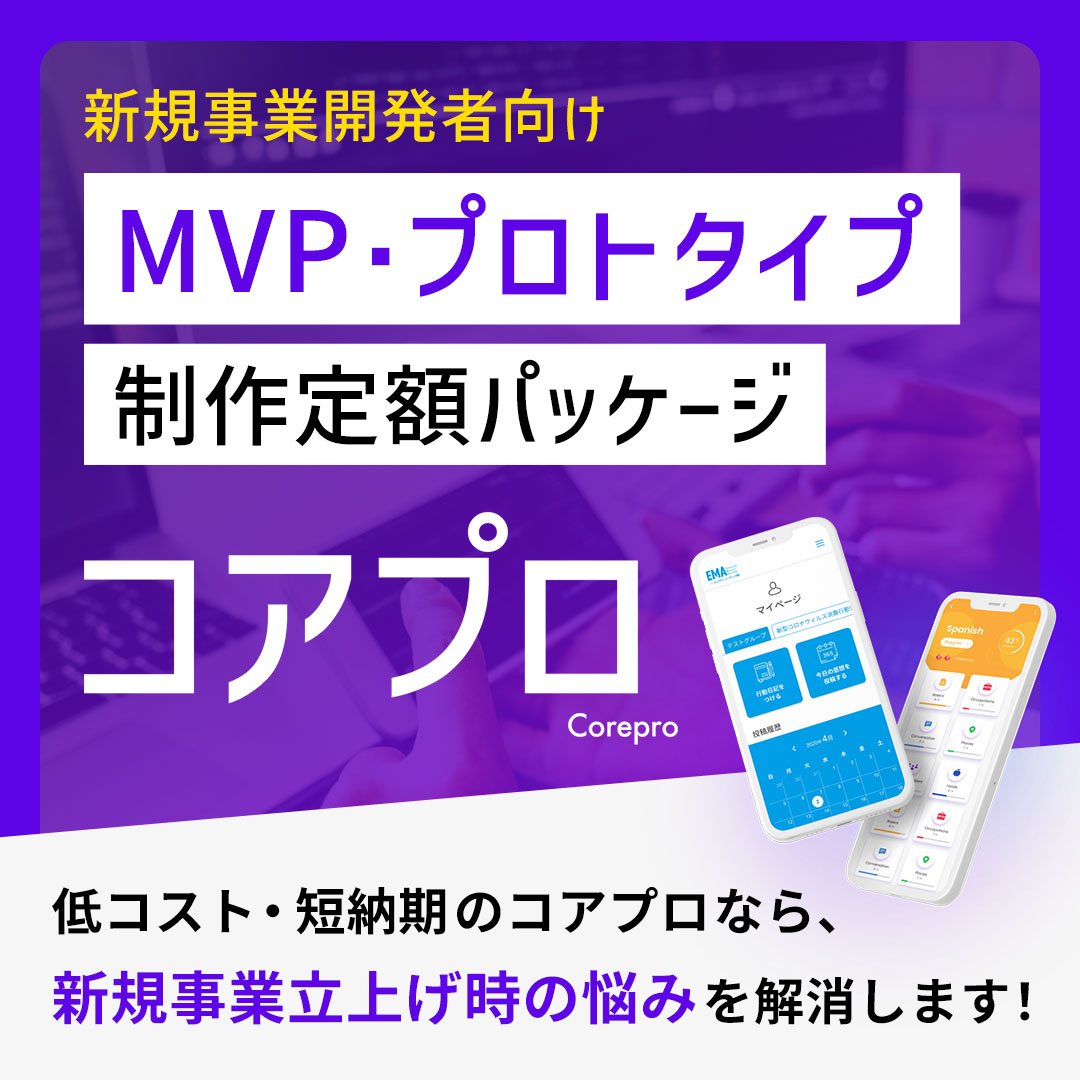新規事業を始める際、適切なフレームワークを活用することは非常に重要です。フレームワークを理解し、活用することで、予想外の損失を避け、成功への道筋を描くことができます。
本記事では、新規事業の各フェーズに適したフレームワークを具体的に解説します。フレームワークを活用することで、新規事業の失敗リスクを軽減できる理由についても説明します。
新規事業を成功に導くためのフレームワークについて、ぜひ最後までお読みください。
新規事業の立ち上げにフレームワークが役立つ理由
新規事業を立ち上げる際、フレームワークを活用することで思考を整理し、検討事項を体系的に整理することができます。これにより、重要な要素を見落とすことなく、効率的な議論を行うことが可能になります。
フレームワークを適切に活用することで、問題解決までの道筋を明確化し、無駄なく進めることができるでしょう。ただし、その際には新規事業のフェーズに適したフレームワークを選択することが重要です。
また、複数のフレームワークを組み合わせて活用することで、多角的な視点で物事を捉えることができます。実際、多くの企業がいくつかのフレームワークを併用しています。それでは、フレームワークの定義とそれを活用することのメリットについて詳しく解説していきましょう。
フレームワークとは
フレームワークとは、ビジネスにおいて問題解決や思考を整理・改善する際に活用する枠組みをパターン化したもののことです。フレームワークを活用することで、情報を整理することが容易になり、目標を達成するための道のりを明確化することができます。
フレームワークがないと、計画の進め方が分からなくなったり、必要以上の時間や労力をとられてしまうことになるため、適切に使用しましょう。
新規事業でフレームワークを活用するメリット
新規事業でフレームワークを活用すると、下記のようなメリットを得ることができます。
- 時間を節約できる
- 効率的にアイディアを整理することができる
- アイディアの漏れを少なくすることができる
- 情報共有を容易にすることができる
フレームワークを活用することで無駄な検討がなくなるため、時間を節約して効率のいい話し合いの場を設けることができます。また、短時間かつ脱線しづらい方法であるため、集中力を維持しながらアイディアをだし合うことが可能です。
ミーティングのあと、時間を割いて見落としを探す必要もないため、効率よく高クオリティの意見交換ができるようになるでしょう。
フレームワークを活用する際のポイント
フレームワークを最大限に活用するためには、フェーズにあったフレームワークを選定することが重要です。また、1つのフレームワークですべてをカバーできるわけではないため、検討事項を見落とすことがないよう、複数のフレームワークを組み合わせて活用することがポイントです。
フレームワークが万能だと思い込んでしまうと、思い込みやバイアスがかかりやすくなります。その結果、視野が狭くなってしまい、偏った視点で新規事業を検討してしまうことになりかねません。
客観的な視点を意識することも、フレームワークを活用するためには必要なスキルになるでしょう。うまく活用すれば、実現可能性の高い事業を生み出すことが可能です。
新規事業のフェーズ1:領域選択とテーマ設定
新規事業を立ち上げる際、まず取り組むべきは、事業領域の選択とテーマ設定です。顧客や市場のニーズを適切に把握し、自社の強みを活かせる事業を展開することが重要です。
また、事業の軸となる明確なテーマを設定しておくことで、後々方向性がぶれることを防げます。例えば、「この市場で当社がNo1になれる」といった、自社の強みを活かせる分野での事業展開は、競合他社との差別化につながります。
このフェーズで活用できる具体的なフレームワークを4つ紹介します。
①マンダラート:目標達成のための思考展開ツール
マンダラートは目標達成のための思考展開ツールです。マス目の中に目標やテーマを書き込み、話し合いをしながらその周囲に意見やアイディアを記入・発展させていく思考ツールのことです。
大谷翔平選手が目標を達成するために使用したことで有名になったため、活用したことがある人もいるのではないでしょうか。新規事業のテーマを構築する際に利用しやすいため、このフェーズではおすすめの1つです。
②PEST分析:外部要因の分析
PEST分析とは、自社と自社を取り巻く環境が、今後将来的にどのような成果や影響を与えるかを把握・予測するために活用することができます。PESTは政治(Politics)、経済(Economy)、社会(Society)、技術(Technology)という4つの外部環境の頭文字をとっています。
このフレームワークを活用することは、市場トレンドを把握し法規制を理解することに有効です。
③SWOT分析:自社の要因の分析
SWOT分析では、自社の強み(Strength)、弱み(Weakness)、機会(Opportunity)、脅威(Threat)を把握し分析するフレームワークです。内部環境と外部環境を分析することで、自社の強みを活かし、弱みを改善しながら、機会を捉え、脅威に対処するための戦略を立てることができます。
このフレームワークを活用することで、自社に最適な事業展開の方向性を見出し、将来的なリスクにも備えることができるでしょう。
④3C分析:自社と市場の環境分析
3Cとは、「顧客(Customer)」、「競合(Competitor)」、「自社(Company)」という3つの要素のことです。それらを分析することで事業の成功要因の分析が可能になります。
市場と顧客のニーズがどのように変化するのか、環境変化によって競合の反応はどのように変化するのか、顧客と競合の反応から自社が成功できる要因はどこにあるのかなど、市場の変化に敏感に対応するためには、必要不可欠なフレームワークといえるでしょう。
新規事業のフェーズ2:事業計画作成
領域やテーマが選定されたら、次に具体的な事業計画を作成します。事業計画は、社内のリソースを獲得し、関係者から推進してもらえるような内容でなければなりません。
曖昧で実現可能性の低い計画では、社内会議で却下されてしまう恐れがあります。ここでは、事業計画作成に役立つおすすめのフレームワークを4つ紹介します。
①ビジネスモデルキャンバス(BMC):ビジネス全体を可視化
ビジネスモデルキャンパスは、事業全体を客観的かつ俯瞰的に捉え、顧客セグメント、価値提案、チャネル、コスト構造、収益源を視覚的に把握することができるフレームワークです。視覚化することは、組織内で共通の認識を持つことにつながるため、顧客や市場のニーズに寄り添ったビジネスモデルを検討することが可能になります。
また、自社だけではなく他社のモデルキャンパスを作成することでどのように違いがあるのかを比較・検討できるため、競合分析に対しても有用性があります。
②リーンキャンバス:アイディアを可視化
リーンキャンバスは、スタートアップ向けの事業計画フレームワークであり、仮説検証に基づくビジネスモデルを作成することが可能です。比較的短時間での作成を期待できるため、効率よく複合的業務をこなすことが期待されます。
顧客・製品・課題に着目して、問題点を把握し、改善できます。
③バリューチェーン分析:ユーザーに提供するまでの流れを工程ごとに分析
自社の事業プロセスがどのように価値を生み出しているかを分析し、競争優位性を見つけるのに役立つフレームワークの1つです。バリューチェーンは「価値の連鎖」と訳されているほど、商品やサービスを生み出すことから消費者の手にわたるまでの過程・価値を考慮したマーケティング手法です。
無駄なコストをカットしたり、消費に伴う製品の在庫管理など細かい部分を修正・検討することができます。
④フィージビリティスタディ(実現可能性調査):事業成功の可否を評価
事業の実現可能性(フィージビリティ)やリスクを調査・分析・検証することで、投資に値する事業計画なのか、計画の精度は高いものなのかを判断するために有用なフレームワークです。調査対象は、政治や社会情勢、財務、自然環境、市場動向など多岐にわたります。
新規事業が自社にとって有益なものかを総合的に判断することができます。特に、海外市場への進出を視野に入れた新規事業の場合、フィージビリティスタディは欠かせない手法といえるでしょう。
新規事業のフェーズ3:事業立ち上げ
事業計画が完成し、社内でゴーサインが出たら、いよいよ本格的に事業を立ち上げていきます。計画を実行し、製品やサービスを市場に投入する段階です。
ここでも有用なフレームワークを活用することで、事業開始直後の予期せぬ問題に柔軟に対応することができます。このフェーズでおすすめのフレームワークを2つ紹介します。
①PDCAサイクル:マネジメント品質向上
PDCAサイクルは、多くの企業で広く活用されているフレームワークです。事業立ち上げ後、課題を発見し改善するためのサイクルを回すことで、品質を高めていく手法です。
計画(Plan)、実行(Do)、測定・評価(Check)、対策・改善(Action)のプロセスを繰り返すことで、やるべきことや対策を明確化し、事業の問題点に継続的に対応することができます。また、このサイクルを通じて得られた知識やノウハウを蓄積することで、スタッフの育成にも役立てることができます。
②OKR(Objectives and Key Results):目標管理
OKRは、目標と結果の管理を行うことができる手法です。事業の進捗状況や、スケジュール調整の必要性など、組織全体の目標設定と進捗管理に活用できます。
達成目標(Objectives)と、主要となる成果(Key Results)を設定することで、関係者が共通の重要課題に取り組めるようになります。優先順位をつけることにより、生産性の向上とコミュニケーションの活性化を図ることが可能です。 Google、メルカリ、Chatworkなど、多くの企業で導入されており、信頼性の高いフレームワークといえます。
新規事業のフェーズ4:事業拡大
新規事業を立ち上げたあとの課題は、事業をどのように拡大し、市場シェアを増やして収益化を図るかという点です。事業が思うように進まず赤字が続く場合、具体的な対策や新たな製品・サービスの導入が必要になります。
このような最終フェーズで活用できるフレームワークを3つ紹介します。
①アンゾフの成長マトリクス:成長戦略の方針を策定
「戦略的経営の父」と称されるイゴール・アンゾフによって提唱された、事業の成長・拡大に関するフレームワークです。既存市場の拡大や新市場進出の戦略策定に活用できるため、このフェーズに適しています。
事業の成長を「製品」と「市場」の2軸で分け、さらに「既存」と「新規」に2分割したマトリクスです。4つのセクションから企業の成長戦略オプションを抽出することで、サービスや製品を問わず幅広いビジネスに適用可能です。
②ブルーオーシャン戦略:新市場を開拓する経営戦略論
ブルーオーシャン戦略とは、競争の激しい既存市場(レッドオーシャン)ではなく、まだ競争のない未開拓市場(ブルーオーシャン)を開拓することを目指す経営戦略です。2005年にW・チャン・キムとレネ・モボルニュによって提唱されました。
競合がいないため競争優位性を持つことができ、今まで存在していなかった新しい分野・領域に事業を展開することが可能になります。
ブルーオーシャン戦略の実践方法
- 市場の現状分析(戦略キャンバスの作成)
- 新しい価値の創造(ERRCグリッドの活用)
- プロトタイプやテストマーケティング
- 競争市場に戻らない仕組みづくり
ブルーオーシャン戦略の成功事例
- シルク・ドゥ・ソレイユ(サーカス)
- 伝統的なサーカスから動物の使用を排除し、アクロバットと芸術性を融合した新しいエンターテイメントを創造。
- ニンテンドーWii
- 高性能競争を避け、直感的なモーション操作を採用することで、新たな顧客層(ファミリー層・高齢者層)を開拓。
- スターバックス
- 「ただのコーヒー販売」ではなく、居心地の良い「第三の場所(サードプレイス)」を提供。
③GEマトリクス(成長-シェアマトリクス):ポートフォリオ・マネジメント
事業の成長性と市場シェアを分析し、どの事業にリソースを投入すべきかを決定するためのフレームワークです。3×3のマトリクスで構成され、縦軸に「業界の魅力度」、横軸に「業界での自社の地位」を設定し、9つの事業タイプに分類します。
それぞれの事業にどのようにリソースを配分するかを検討するためのフレームワークであり、ゼネラル・エレクトリック社(GE)とマッキンゼー社によって提唱された手法です。
まとめ
新規事業を立ち上げる際、適切なフレームワークを活用することで、情報の整理・共有が容易になり、目標達成に向けた解決策を見出しやすくなります。また、効率的な議論を短時間で行えるのも、フレームワークの魅力の1つです。
新規事業を始める際は、各フェーズの目的に応じて適切なフレームワークを選択することが重要です。本記事で紹介したフレームワークを参考に、事業計画の検討や課題解決に役立ててください。
さらに、新規事業に必要な資料作成をサポートするWEBサービスも活用することで、より効果的な事業展開が可能になるでしょう。